| 指標一覧 |
|
■ RCI(Rank Correlation Index) ■ SRV%K %D %SD ■ ボリンジャー(Bollinger Band) ■ 一目均衡表 ■ DMI(Directional Movement Index) ■ MACD(Moving Average Convergence and Divergence) ■ ボリュームレシオ(Volume Ratio) ■ RSI(Relative Strength Index) ■ 価格帯レシオ ■ ベクトル ■ パラボリック(Parabolic−SAR−) ■ カギ足 ■ サイコロジカル(Psychological line) ■ 新値足 ■ ORレシオ ■ 大引陰陽足 ■ モメンタム(Momentum) |
| RCI(Rank Correlation Index) |
|
順位相関係数とも言う。単一の商品(銘柄・指数)において時間の推移と価格の水準それぞれに順位をつけ、相関関係があるかどうかを見るテクニカル指標である。 利用方法は主に2つに分類できる。ひとつは2期間のRCIをとり、2本の線のクロスを転換のサインとする。もうひとつは、RCIが底値圏もしくは高値圏(±80%の水準)から反対方向へ切り返した場合に転換のサインとする方法である。 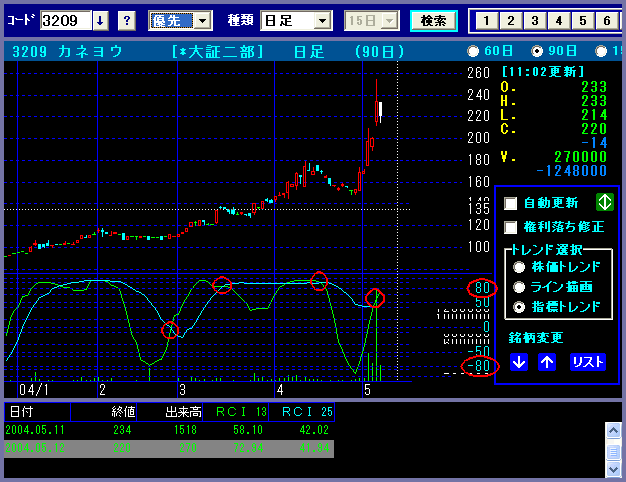 指標一覧へ戻る |
| SRV%K %D %SD |
|
ここでいう「SRV」とはストキャスティクス(Stochastic)のことを示しており、価格の終値の位置と定められた日数の価格範囲を比較するオシレータ指標のことを言う。
SRV%Kは期間内の最高値および最安値から見た終値の位置を表しており、%Dは%Kを平均化したもの、%SDは%Dをより一層平均化したものである。
一般的な使用法は以下の3つ。 1.オシレータ(%K・%Dいずれでもよい)が予め定められた水準(例:20%以下)を割った後、下から上抜ける時に買いポジションを取る。売りポジションの場合はその逆(例:80%以上)となる。 2.%Kラインが%Dラインを上に抜ける時、買いポジションを取り、%Kラインが%Dラインを下抜ける時、売りポジションを取る。 3.株価が高値を更新しているにも拘らず、オシレータが前回高値を超えずに調整する場合に売りポジションを取る。買いポジションはその逆をいう。 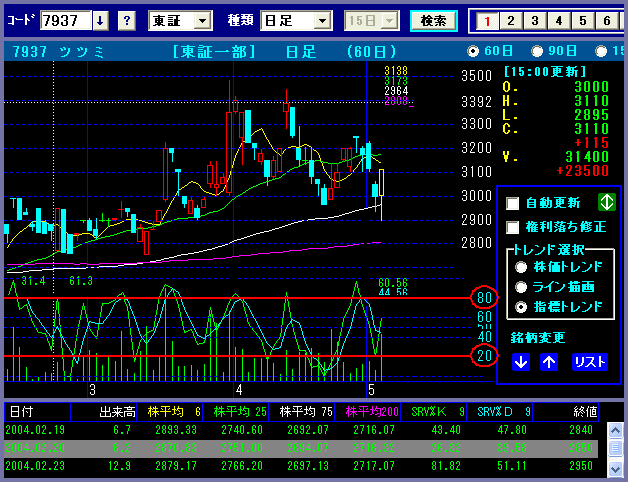 指標一覧へ戻る |
| ボリンジャー(Bollinger Band) |
|
ボリンジャーバンドとは、ある期間の移動平均値と標準偏差をその上下に加減した、一種のオシレータ指標である。
標準偏差(±σ)が統計上データの約68%の範囲、標準偏差の2倍(±2σ)が約95%の範囲を規定する数値であることから、株価は以後±σ範囲内では約68%、±2σ範囲内では約95%の確率で推移すると考えられることになる。 バンドそのものがサポート及びレジストとして機能するため、下方のライン付近で押し目買い、上方のライン付近で戻り売りをするのが一般的。 注意すべき点としてはトレンドの有無であり、明らかにトレンドが発生している場合には、バンドブレイクの段階でその方向に沿ったポジションを取らなければいけない。 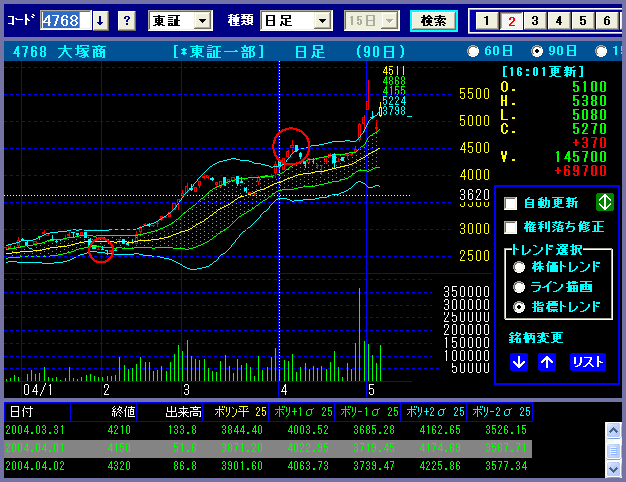 指標一覧へ戻る |
| 一目均衡表 |
|
一目均衡表とは故一目山人翁が編み出した相場分析手法であり、時間論を主軸として波動論・水準論の3本柱からなる、総合的かつ体系的な分析指標である。一目均衡表はローソク足と、同時に記入された5本の折れ線グラフ(転換線・基準線・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン)から構成されており、各々の線の位置関係により株価分析を図るものである。 見方としては以下の通り。 1.転換線が基準線を上抜けると「好転」(強気相場)、下に抜けると「逆転」(弱気相場)。 2.「雲」(先行スパン1と先行スパン2との間)を抵抗帯として捉え、この抵抗帯をローソク足が通過するときに、それまでの方向に対してレジストする性格が強い。 3.ローソク足が基準線の上位に位置している場合は上昇基調であり、下方に位置している場合は下降基調。 4.遅行スパンが26日前のローソク足を上抜けした時(遅行スパンが好転した時)は反転の兆しであり、遅行スパンが26日前のローソク足を下に抜けた時(遅行スパンが逆転した時)は下落の兆しとなる。 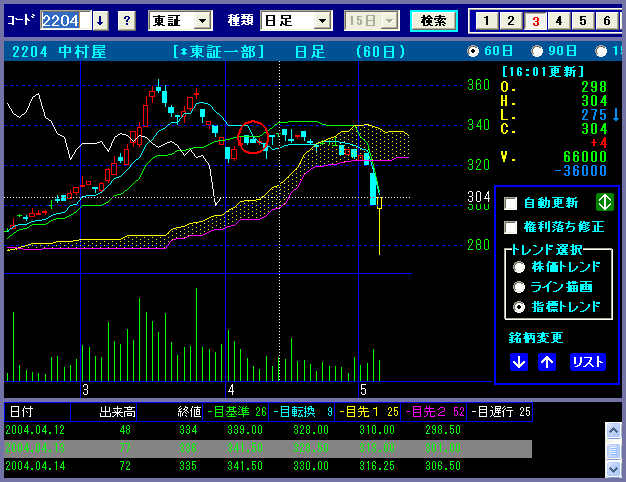 指標一覧へ戻る |
| DMI(Directional Movement Index) |
|
方向性指数とも言う。テクニカル分析では主にトレンド系分析(トレンド追随型分析)とオシレータ系分析(逆張り型分析)の2つに大きく分けられている。相場分析において、一方が機能する場合は他方がそうでないケースが多いため、市場の様相においてどちらの分析を選択するかが非常に重要なポイントとなるわけだが、このDMIを用いることによって、トレンドの有無だけでなくトレンドの強弱までも推し測ることができる。 DMIは「DM」「TR」「ATR」「DI」「ADX」「ADXR」から構成され、主に「DI」や「ADX」、「ADXR」を軸に分析をすることになる。 1.トレンドの方向 +DIラインが−DIラインより絶対値が大きいときは上昇傾向、小さいときは下落傾向となる。また、その差が大きければトレンドの勢いは強いと解釈される。 2.トレンドの大きさ ADXの動きに注目し、上昇基調ではトレンドに沿った動きをしていると考えられ、下落基調にある場合はトレンドに沿った動きから離れている状態を示していると判断する。よって、その傾きで勢いを推し量るのがトレンドに乗り遅れないポイントになる。ただ、騙しを避けるために一定の水準以上(30など)の場合にトレンドを認識する方法などがある。 3.トレンドの有無 ADXとADXRとの位置関係に注目し、ADXがADXRより上の位置にある場合はトレンドが存在し、ADXがADXRより下の場合はトレンドレスとなる。 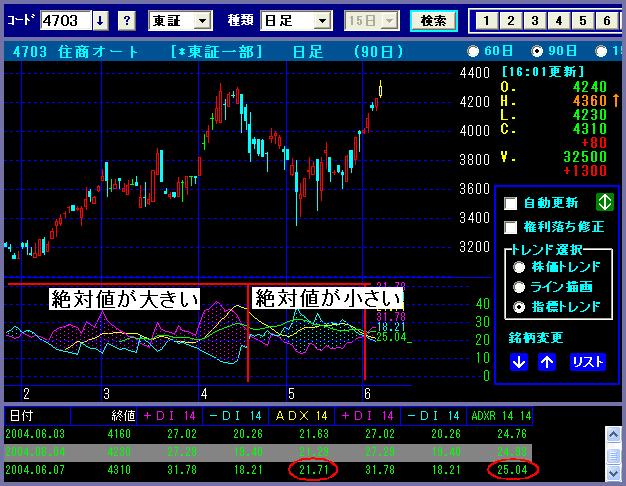 指標一覧へ戻る |
| MACD(Moving Average Convergence and Divergence) |
|
移動平均収束発散法とも言う。このMACDは2つの加重平均もしくは平滑移動平均の間の差を計測するものである。一般的に、短期の移動平均は長期の移動平均よりも現在の市場価格に近い位置で推移するものであり、普通上昇相場の場合、短期の移動平均が早めに反応するため、長期の移動平均と大きなギャップ(乖離)を形成する。MACDとはこのギャップを計測するためのものである。 主な使用方法としては以下の通り。 1.市場価格が高値を更新しながら推移しているにも関わらず、MACDが高値を更新できない場合は「発散売り」(Divergence Selling)となる。また、その時点においてMACDがシグナル線より下にクロスして下落していくと特に強い売りサインを形成する。 2.市場価格が安値を更新しながら推移しているにも関わらず、MACDが安値を更新しない場合は「収束買い」(Convergence Buying)となる。また、その時点においてMACDがシグナル線を上回った場合は特に強い買いサインを形成する。 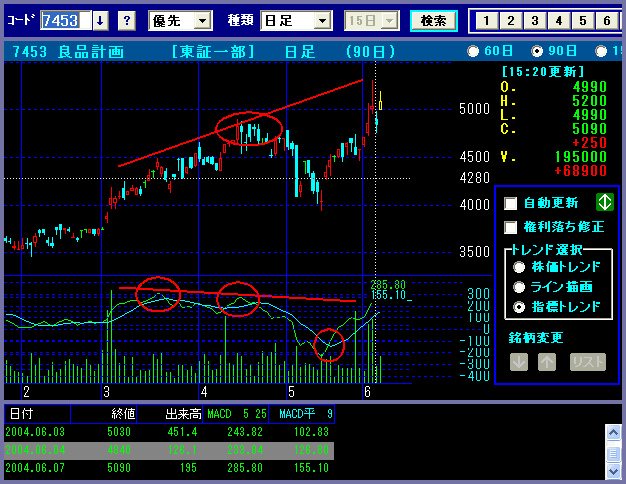 指標一覧へ戻る |
| ボリュームレシオ(Volume Ratio) |
|
一定期間を区切って、その間の株価上昇日の出来高合計と株価下落日の出来高合計の百分比を出したものが、このボリュームレシオ(VR)である。VRが100%の水準では株価上昇日の出来高合計と株価下落日の出来高合計が同じで、110%では株価上昇日の出来高合計が株価下落日の出来高合計よりも10%多いことを示すわけである。経験的には株価が上昇する日の出来高は、株価が下落する日の出来高よりも多い傾向にあり、100%を中心に上下動を繰り返すこのVRは下振れよりも上振れの方が多いのが特徴である。 この指標の使用法として、現在どの水準に位置し、またどちらの方向に向かっているかが重要となってくる。例えば株価ピーク時に買われすぎを示す高VR値を出すこともあれば、上昇初期段階においても高VR値を出すこともあるので、その際には注意が必要である。 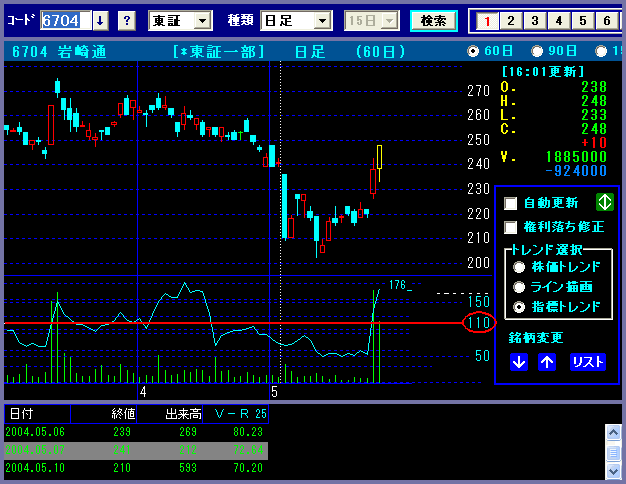 指標一覧へ戻る |
| RSI(Relative Strength Index) |
RSIはSRVと同様、パーセントをY軸に取る指標であり、その水準によって買い超・売り超を判断するオシレータ系指標である。具体的には、一定期間の価格上昇日の前日比値上がり幅合計を、同期間の価格下落日の前日比値下がり幅合計で除したものである。50%を中心に上下にエッジバンドを設け、指数レベルの70%以上を買い超(売りシグナル)・30%以下を売り超(買いシグナル)と判断するのが一般的な見方であろう。また、価格と比較したRSIの動きも重要なポイントになる。これはオシレータ系指標全般に言えることだが、価格とのダイバージェンス・コンバージェンスからトレンド変化を読み取ることができるのである。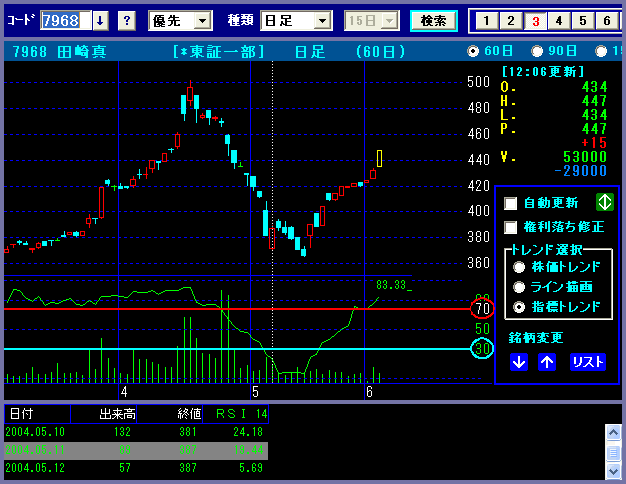 指標一覧へ戻る |
| 価格帯レシオ |
一定期間内の終値価格ごとの出来高累計を棒グラフ状に表したものである。出来高累計が多くなればなるほど、その価格でレジストあるいはサポートされる可能性が高い。具体的な使用方法としては、価格より上方に厚いボリュームラインが横たわっている場合、その価格帯が上値抵抗帯を形成、売りポイントを示すこととなり、逆に価格より下方に厚いボリュームラインが横たわっている場合、その価格帯が下値抵抗帯を形成、買いポイントを示すこととなるわけである。しかし、最上位あるいは最下位ボリュームラインを突破し、新値模索を続ける段階においては、価格帯レシオだけでサポートラインを見つけることは不可能であるため、以前の高値・安値と価格の比較等からトレンド変化を読み取る必要がある。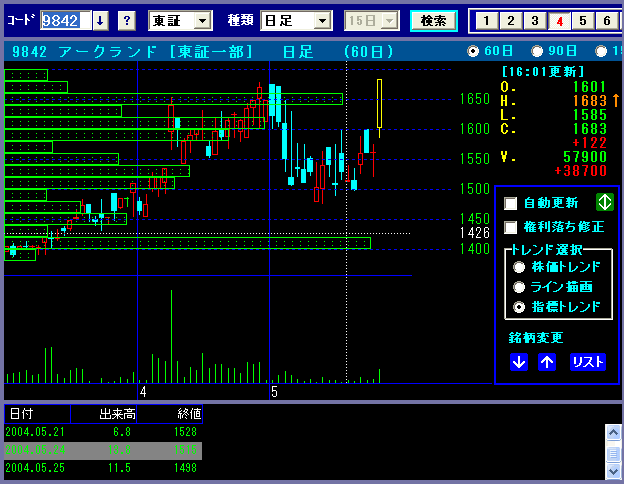 指標一覧へ戻る |
| ベクトル |
回帰曲線指数とも言う。価格騰落の速度変化を大引値のみで計算し、価格上昇あるいは価格下降の速度と日数の相関関係を一次直線で導き、さらにその傾きを一次式に回帰させた指標である。この勾配は目先の価格変動に惑わされることなく滑らかに推移する為、一定期間内のトレンドを的確に把握出来、上値・底値の転換点を捉えるのに非常に有効である。一般的な使い方としては、ゼロラインの下方に位置しつつ、ベクトルおよびベクトル平均線がゴールデンクロスを示現した所を買いポイントとし、逆にゼロラインの上方に位置しつつ、ベクトルおよびベクトル平均線がデッドクロスを示現した所を売りポイントとする。また、値動きの激しい商品においては、ベクトルが-15%を上抜けした所で買い、+15%を下回ってきた所で売る、といった投資手法も有効的である。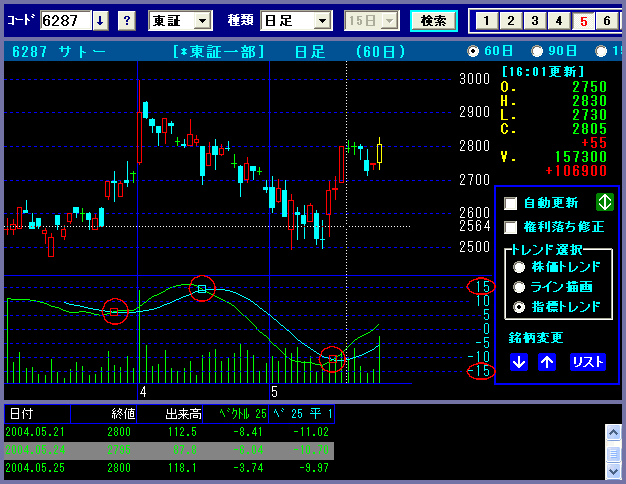 指標一覧へ戻る |
| パラボリック(Parabolic−SAR−) |
|
パラボリックとは、価格の動きに時間の要素を盛り込んだシステムで、大きなトレンドは逃さず捕らえ、トレイリングストップを用いることにより、新高安値更新や時間の推移をいち早く反映することをコンセプトにしており、通常のオシレータ系システムでのシグナル発生の遅行性および、市場の勢いを推し量る上での時間の要素の欠如を補うことが出来るものである。 見方としては、価格がパラボリックにサポートもしくはレジストされている間は、そのトレンドが継続している(上昇トレンド・下降トレンドにある)とみなし、ポジションをキープする。しかし、一旦ブレイクするとトレイリングストップを採用し、ポジションをひっくり返すのである。また、騙しを避けるため、例えばエントリーは移動平均線付近から行い、クローズポイントのみパラボリックを用いる、といった活用法もある。 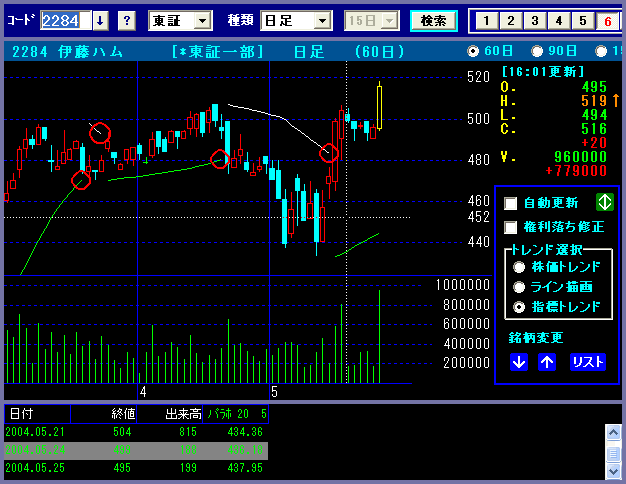 指標一覧へ戻る |
| カギ足 |
カギ足は別名「値幅足」ともいい、価格の騰落を線状で表した指標である。一定幅あるいは一定率以上の価格変化からトレンドを推し量るものであり、前者を定額法カギ足、後者を定率法カギ足と呼ぶ。カギ足は日足そのものに比べ価格の変動傾向が掴みやすくなっており、例えば値幅を大きく取れば中長期トレンドを把握しやすい反面、遅効性という問題が生じてくる。反対に、値幅を小さく取れば短期トレンドを把握しやすいが、騙しが多くなってくるわけである。具体的な見方としては、カギ足が直前の肩を抜いたところで買いポイント、直前の腰を下回ったところで売りポイントとなる。同じ一段抜きでも中心線を切らずに上昇すれば、買い圧力は強いことを示し、一方、中心線を抜かずに下落すれば、売り圧力は強いことを示すことになる。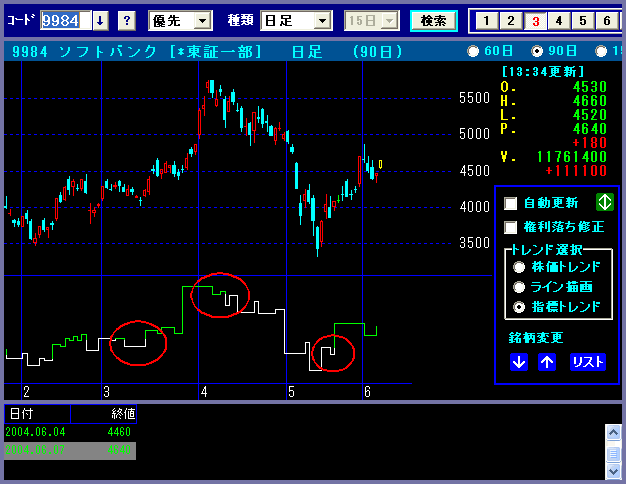 指標一覧へ戻る |
| サイコロジカル(Psychological line) |
|
サイコロジカルラインとは、一定期間における前日比価格上昇日数の割合を示したものである。 その名の通り、「上昇すればするほど強気に傾き、下落すればするほど弱気に傾きがちになる」といった投資家心理そのものを指数化したものであり、ここに上昇幅・下落幅の要素を加味したものが別掲のRSIになる。一般的に30%の数値を上抜ければ買い、75%の数値を下回ってくると売りとなるわけだが、値動きの激しい商品(個別銘柄等)に対しては騙しが非常に多くなってくるため、出来れば日経平均やTOPIXといった代表指数に用いるのがよいとされている。 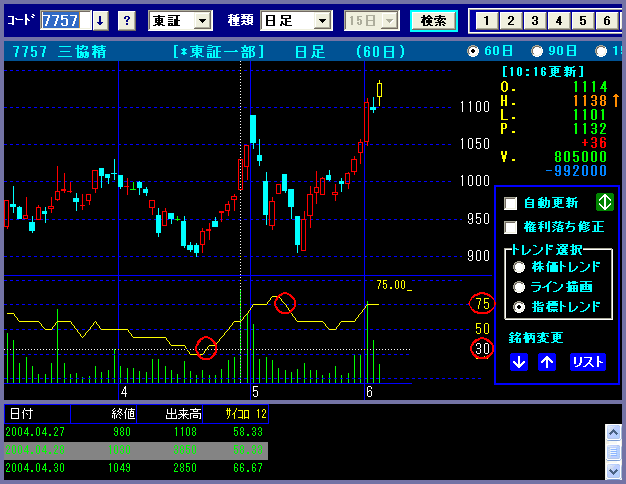 指標一覧へ戻る |
| 新値足 |
新値足とは、大引値が新値を抜く都度に陽線・陰線を記入して出来る指標のことであり、直前の陽線(陰線)3本分を抜いた場合右側に新しく陽線(陰線)を加えていくものを「三本新値足」という。陰線から陽線に変わることを「陽転」といい、すなわち買いポイントとなる。反対に、陽線から陰線に変われば「陰転」ということになり、売りポイントとなるわけである。しかし、中段保ち合いの場面では、非常に多くの騙しが発生しやすい為、2本目の陽線(陰線)で買う(売る)といった工夫が必要となってくる。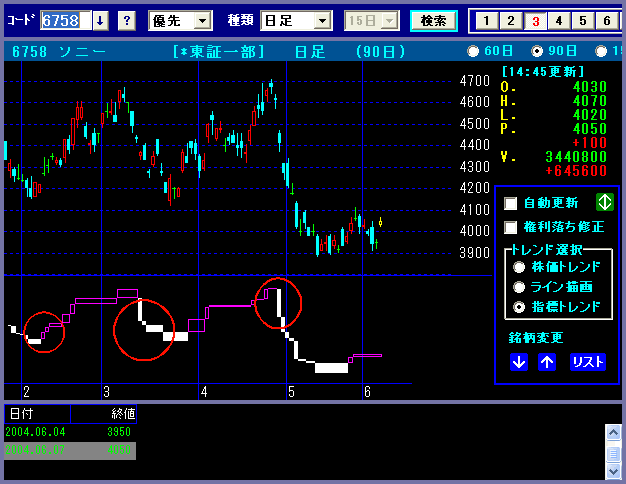 指標一覧へ戻る |
| ORレシオ |
|
ORレシオの「O」とは「opportunity」、「R」とは「risk」を表し、これを訳して「期待・危険係数」とも言う。一定期間内の高安値から見て現在の価格水準がどの位置にあるかを探ろうとする指標であり、高値に近ければ近いほど売り圧力が強いことを示し、一方で安値に近ければ近いほど買い圧力が強いことを示している。一般的な使い方としては以下の通り。 1.Rレシオがゼロに近い水準から陽転、Oレシオが25以上にある時、もしくはその水準から陰転した時に買いポジションをとる。 2.Oレシオがゼロに近い水準から陽転、Rレシオが25以上にある時、もしくはその水準から陰転した時に売りポジションをとる。 ただし、期間内の高安値を意識した相場展開という大前提があるため、頻繁に新高安値を更新する場面においては使用時に注意しなければならない。 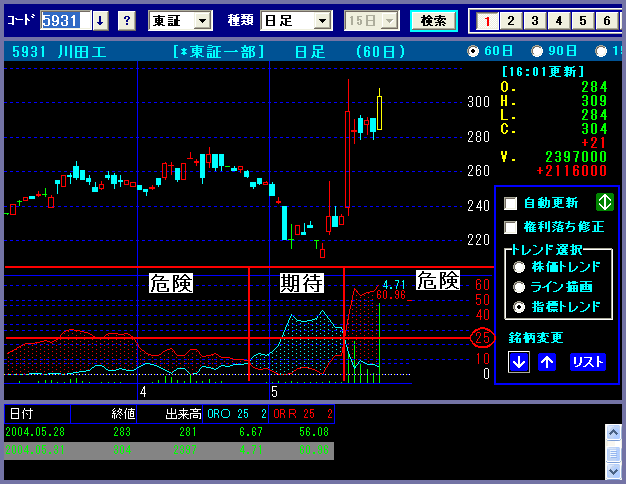 指標一覧へ戻る |
| 大引陰陽足 |
前日の大引値と当日の大引値を陰陽線で結んだものである。新値足と似通った指標であるが、最大の違いは大引け値だけに注目した点にあり、極力トレンドに対するタイムラグを少なくするように設計されている。この指標は単独で用いるべきでなく、他のオシレータ系指標と併用するのが一般的。例えばサイコロジカルが保ち合い相場を示す50%水準にあった場合、トレンドを見極める際に使用する、といった使い方ができるわけである。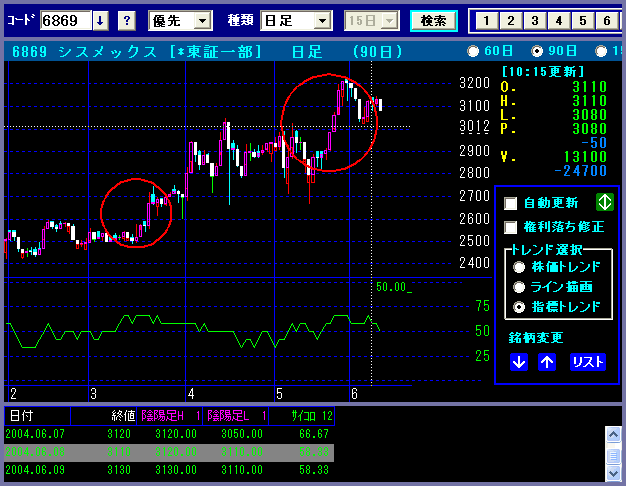 指標一覧へ戻る |
| モメンタム(Momentum) |
一般的にモメンタムとは一定期間内における価格の変化値を表す指標であるが、ここでは一定期間内の移動平均線の変化率を指す。もちろんこの数値が大きくなればなるほど、価格に対する騰勢が強いことを示し、逆に小さくなればなるほど下降基調に拍車が掛かっていることを示すわけである。しかし、ここで注意が必要なのは、モメンタムが反転しても価格のトレンドが反転したことにはならないことである。例えば25日移動平均線で見た場合、一時的に変化率が回復を見せたとしても、それは単なる自律反発に過ぎず、さらなる下降トレンドに続くケースも十分に考えられる。そこで、ゼロラインとクロスした場合にトレンド変化したと判断するのが良いだろう。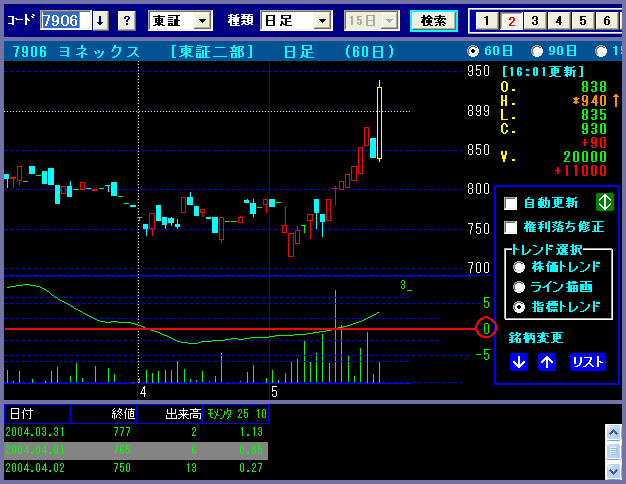 指標一覧へ戻る |